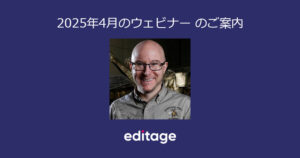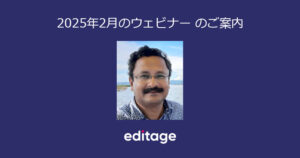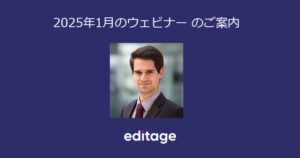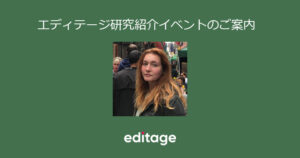今年度のRA協議会第10回年次大会では、東京科学大学の主任URA、原田隆氏を座長に「待ったなし!2025即時OA対応に大学、そしてURAは今後何ができるのか」というテーマで、パネルディスカッションが開催されました。
「公的資金によって生み出された論文や研究データ等の研究成果は国民に広く還元されるべきものである」という考えから、2024年2月に内閣府の統合イノベーション推進会議より「学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針」が公表されました。公的資金による助成を受けた学術論文等(2025年度新規公募分より)は即時オープンアクセス(OA)を義務化するというものです。
セッションは、研究者の現状認識および声、政策の背景を踏まえて、大学そしてURAは「学術論文等の即時オープンアクセスの実現」に対してどのように貢献できるかを議論することを目的に実施され、林和弘氏(文部科学省 科学技術・学術政策研究所)、天野絵里子氏(京都大学)、湯浅誠氏(カクタス・コミュニケーションズ株式会社)の3名による発表と、会場に集った全国のURAの皆様とディスカッションが行なわれました。この記事では、その発表と議論のポイントをダイジェストでお伝えします。
このレポートは、リサーチアドミニストレーション協議会(RA協議会)第10回年次大会セッション「待ったなし!2025即時OA対応に大学、そしてURAは今後何ができるのか」(2024年10月17日、沖縄科学技術大学院大学)における発表およびディスカッションをまとめたものです。 公式サイトの情報はこちらから
大学やURAに求められる即時オープンアクセス化とは

原田 隆
東京科学大学 主任URA
プロフィール
産総研特別研究員、NEDOフェロー、筑波大学アシスタント・コーディネーター、福井大学URA、東京工業大学(現東京科学大学)特任助教を経て2017年6月より研究・産学連携本部 プロジェクト推進部門URA(情報理工学院担当)。2020年4月、情報理工学院に所属変更。2020年9月、主任URAに昇進。現在はJST共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)のポストアワード業務を担当。
ウェブサイト
座長の東京科学大学の原田です。本セッションのテーマは「待ったなし!2025即時OA対応に大学、そしてURAは今後何ができるのか」です。今回のセッションでは、2025年からのオープンアクセス義務化に向けて、研究者や関係者がどのように対応すべきかについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
オープンアクセスの基本的な定義は、「誰でも無料で自由にアクセスでき、内容の改変や再利用が可能」であることです。しかし、実際の運用では制限がかかる場合もあります。日本では、2025年から採択された研究に関連する学術論文やデータがオープンアクセスの対象となりますが、すべての研究データが対象になるわけではなく、公開が求められるのはあくまで透明性が求められる研究データに限られます。査読付き電子ジャーナルが対象であり、紙媒体のものは含まれません。
セッションでは、オープンアクセスの実施に向けた準備と、その義務化がなぜ必要かについて触れていきます。義務化という言葉が強調される理由は、研究データの共有と透明性を高め、学術コミュニケーションをよりオープンにするためです。オープンアクセスを実現するための具体的な手順としては、内閣府のホームページを頻繁にチェックすることが推奨されます。UIを整えた上で公開すればオープンアクセスとみなされること、著作権やクリエイティブコモンズの利用についても確認する必要があることなどが記載されていますが、更新が早く重要な情報が変わることも多いため、定期的に確認することが大切です。
まずは湯浅さんから「即時オープンアクセス義務化に対する研究者の意識調査」の結果を発表していただき、後半はオープンアクセスに関する研究者の現状と、URAの役割についても詳しく説明していきます。林さんが疑問を解決する形で解説し、天野さんがURAの役割や注意すべき点を説明してくれるので、参加者はしっかりと理解を深めることができるでしょう。セッション終了後には、皆さんが自信を持ってオープンアクセスに取り組めるようになることが確約されていますので、安心して参加してください。
-原田氏の発表スライド-