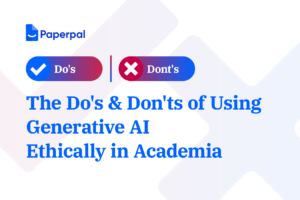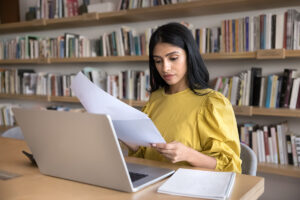出版は本当に研究論文のプロセスの最終章なのでしょうか? 必ずしもそうではありません。多くの点で、出版は出版後査読(post-publication peer review – PPPR)という新たな段階の始まりに過ぎません。これは、より広範な研究コミュニティが参加し、議論を活発化させ、精査をさらに深める段階です。従来の査読が依然としてゴールドスタンダードである一方で、出版後査読が認知されつつあるのには十分な理由があります。まず、通常、より迅速なフィードバックが得られます。また、出版後査読はオープンで公開されていることが多く、多様な研究者が意見を述べることができます。従来の査読は時間がかかり、査読者の多様性に欠けるという不満が多いことを考えると、これは大きなプラスです。編集者への読者からの手紙、ソーシャルメディアのスレッド、あるいはPubPeerやF1000 Researchのようなプラットフォームなど、出版後査読は研究に関する議論において貴重な存在となっています。これらのチャンネルは、過去に発表された研究の欠陥を発見するのに役立ってきました。そして、誤った情報が蔓延し、科学に対する社会的信頼が逼迫している今、出版後であっても透明性を高めることは、これまで以上に重要です。
1. 従来の査読を補完する
従来の査読とは異なり、出版後査読では、より幅広い専門家による出版物の継続的な評価が可能となり、通常はひと握りの専門家しか参加しない初回の査読では見落とされた可能性のある欠陥や誤り、整合性に関する潜在的な懸念を特定することができます。出版後査読はまた、学際的な対話を促進することもでき、様々な分野の研究者による多様な視点が、研究の価値を高め、研究の強化に役立ちます。このような継続的なフィードバックは、信頼性を高めるだけでなく、より協力的でオープンな研究文化の促進にもつながります。
2. 透明性と説明責任の文化を奨励する
出版後査読は、閉鎖的とみなされる出版システムにおいて透明性を高める手段を提供します。オープンな議論と訂正を奨励することで、出版後査読は出版された研究の継続的な精査と評価を可能にし、ジャーナルのコンテンツの信頼性を高めます。さらに、プレプリントや査読者レポートの開示といった他の要素と組み合わせることで、出版後査読はより大きな効果を発揮し、複数の段階で透明性を高める可能性を持っています。このアプローチは、研究者や出版社の説明責任を強化するだけでなく、読者からの信頼も築き、学術コミュニティ内でのジャーナルの地位を高めることもできます。
3. 出版社が科学的記録の正確性を維持するのを支援する
出版後査読が可能にするようなオープンな議論は、出版後も長期にわたって研究の継続的かつ動的な評価を促進することで、ジャーナルが論文の正確性を確保するために、正誤表や訂正、撤回の必要性を判断するのに役立ちます。出版社はまた、出版後査読の事例から得られた知見を活用し、将来の不正行為を防止するための安全策を強化することで、ジャーナルの信頼性を維持することもできます。さらに、出版後査読プラットフォームは、研究者と出版社が協力して研究結果を改善し、懸念事項に対処し、著者と出版社の関係を改善するための動的な場を創出し、著者とコミュニティを研究コミュニケーションと研究発表の中心に置くことができます。
出版後のコメント欄を開放することは、社会的信頼の構築に大いに役立ちます。編集の更新をより透明で効率的なものにし、安全な内部告発を支援し、エビデンス統合のより良い利用を促します。また、COVID-19のパンデミックの際に見られたような一刻を争うときに本当に重要となる、誠意ある協力体制も生まれます。
一方で、このようなシステムには確かなメリットがある一方で、課題がないわけではありません。出版後査読に伴ういくつかの課題を見てみましょう。
1. エンゲージメントの低さ
出版後査読が直面する主な課題のひとつは、出版後にフィードバックを提供する研究者や査読者の数が限られているため、エンゲージメント(参加率)が低いことです。研究者は多忙なため、特にフィードバックが認識されなかったり対処されなかったりすると、出版後査読に参加するモチベーションが高くならないことがあります。フィードバックを提供する研究者や査読者の参加が限られていると、研究の質を高める出版後査読の有効性が損なわれる可能性があります。参加を促すために、出版社は査読プロセスを簡素化し、研究者が参加しやすくしたり、査読者の貢献を評価することでプロセスにインセンティブを与えたりすることができます。例えば、ScienceOpenでは、出版時にDOlを付与することで査読者の貢献が評価され、査読者はORCIDを通じてリンクされるため、査読活動の検証可能な記録が作成されます。
2. レビューの断片化と標準化の欠如
もうひとつの課題は、出版後査読に関する議論が様々なプラットフォームで断片化し、コメントが見逃されてしまうことです。さらに、プラットフォームによっては非公式な性質があるため、レビューの質に一貫性がないこともあります。このような問題は、包括性と相互運用性の欠如に起因していることが多く、異なるプラットフォームが論文に対して様々なタイプのコメントを提供することになり、情報にアクセスするためのより標準化された方法がないまま、同じ研究について議論しているプラットフォームさえあります。出版社は、よりまとまりのある組織的なシステムを構築する上で重要な役割を果たすことができます。たとえば、ScienceOpenはCrossrefやORCIDといった著名な組織と協力し、自社のプラットフォーム上で出版後査読が矛盾なくシームレスに機能するように努めています。
3. レビュープロセスの悪用の可能性
善意の研究者が貴重なフィードバックを求め、提供しているにもかかわらず、出版後査読 プロセスは荒らしの影響を受けやすく、公開フォーラムでの対立につながる可能性があります。このネガティブな要素への対策として、アカウンタビリティ(説明責任)を中核に据えたシステムを導入することで、辛辣なコメントを減らし、研究参加のためのより包括的な環境を提供することができるようになります。匿名性も考慮すべき要素です。匿名性はスパムや専門外のコメントを助長する可能性がある一方で、匿名性を取り除くと、一部の研究者、特に若手の研究者は潜在的な影響を恐れて、上級研究者の研究を率直に批評することを躊躇するかもしれません。そのため、オープンな出版後査読と匿名の出版後査読のどちらが効果的かという疑問が残り、プラットフォームによってアプローチが異なる可能性があります。例えばPubPeerでは、ユーザーが匿名でコメントするか実名でコメントするか選択することができます。一方、ScienceOpenはより厳格な方法をとっており、コメント投稿者にORCIDプロフィールによる本人確認を求めています。ユーザーがコメントを残すには少なくとも1つの出版物を持っている必要があり、完全なレビューや評価を投稿するには5つの出版物を持っている必要があります。
出版システムへの負担は、不正研究行為の複雑化と相まって、査読の現状に欠陥が生じていることを明らかにしました。厳格さを失うことなく、現代科学の要求に応えるために、査読をどのように再構築すればいいのでしょうか? 学術出版を取り巻く環境は変化し続け、それぞれに特有の課題を抱えています。学術コミュニティは、この変化を乗り切るために、革新的な査読モデルを受け入れ、模索する必要があるかもしれません。出版後査読は、研究の誠実さを高めるだけでなく、説明責任と透明性を強化し、コミュニティの参加を促進し、出版プロセスを迅速化するアプローチを提供します。出版後査読の実践はまた、より弾力性のあるシステムを構築し、研究コミュニティ内でのより大きな協力を促進する可能性も秘めています。
この記事はEditage Insights 英語版に掲載されていた記事の翻訳です。Editage Insights ではこの他にも学術研究と学術出版に関する膨大な無料リソースを提供していますのでこちらもぜひご覧ください。