
科学の『科』とは元々物事を「分ける」という意味を持つ漢字です。例えば『物理』と『化学』を、『動物』と『植物』を、私たちは様々な定義と方法で切り分けて理解しています。その一方で全てのものを厳密に区別することは、必ずしも科学の発展のためにならない場合もあります。今まさに生まれようとしている新しい学問や、今まで誰も思いつかなかったオリジナリティにあふれる研究は、そもそも既存の区分けには収まりません。
2016年エディテージ研究費の採択を受けた衛藤彬史(えとう・あきふみ)さんの研究も、今までの研究領域の区切りではうまく説明できない、新しい手法を使ったものでした。

公共交通機関が成立しない地方の山間部。自治体、大学、NPO、住民の相互連携で地域独自の移送サービスを模索する。
衛藤さんの研究テーマは、過疎地に暮らす高齢者の公共交通空白問題。地方の特に山間部では、人口の減少や最寄りのバス停・駅まで遠いなどの理由で、公共交通の利用が難しくなってしまったお年寄りが多くいらっしゃいます。運転ができる血縁者や頼れる人がおらず、住み慣れた地域を離れざるを得なかったり、危険を承知で自ら運転し、事故を起こしたりしてしまう悲劇を減らしたい。衛藤さんはご自身も東京を離れて地方で暮らしながら、研究者と地元の人々が共同で課題の解決にあたる『アクションリサーチ』という手法で、地域の方々が利用しやすい交通システムの構築を目指されています。
衛藤さん「地方の交通の問題はこれまでも議論はされていて、コミュニティバスや乗り合いタクシーなど、色々なことが試されてきています。ただ1日に2本しかなかったり、病院まで行ったはいいけれど帰れないというような使いにくさがあって、結局は利用されていない。行政や交通事業者、地元でやってみたいことを取りまとめる団体、更には住民の方で1つ合意を形成して、例えばドライバーとして住民の方に出て貰おうとかそういうことができないか。法律制度や交通事業者さんとの利害調整は必要になりますが、それも併せてやっていく。地理的条件や人口は地域によって違うので、それぞれに一番最適な形を作る。研究としてはその過程を見る。実践の領域としては作っていく過程自体を、自分自身が関わりながら促していく、そういうことをやりたいですね」

引っ越しの多い都会暮らしから農村へ。暮らして、関わって気づいた『課題』
衛藤さんは子供のころから関東育ち。京都大学に進学するまで関西に行ったこともありませんでした。現在の主な研究フィールドは兵庫県の篠山(ささやま)市ですが、どのようなきっかけで現在のテーマ、フィールドを選ばれたのでしょうか。
衛藤さん「小さい頃は引っ越しが凄く多かったんです。東京にいて、埼玉に行って横浜に行ってまた東京に戻って。実家のような、ふるさとのようなところがないんですね。ずっとその場所に住み続け、いったん外に出ても帰れる場所があるということに憧れやうらやましさがありました。大学は京都大学で農学部なんですが、3年か4年の時に和歌山のある集落に草刈りボランティアに行って、夜に一緒にお酒を飲んだり星が綺麗だと言ったりして、単純にいいなと思ったんです。場所にも惹かれましたし、そこに住む人たちがとても活き活きしていて、人の繋がりや暮らし方には経済的なお金で測れない価値があるなと感じました」
地方ならではのそうした価値が、時間とともに失われていくことに『もったいなさ』を感じたという衛藤さん。例えば篠山では集落ごとに詩も節回しも異なる民謡が多くありますが、歌えるお年寄りが減り、引き継ぐ人もいないために失われつつあります。文化というのはそういうものなのかもしれないと思いながらも、もう少しうまく伝承・継承できれば守れる可能性もある。地域の方々と触れ合う中で、そんな興味が生まれたと言います。
実際にこの分野を選択されたのは、大学4年で研究室に配属されたとき。修士課程では理論や先行研究を学びながら、京都府内の3つの集落でお年寄りにiPadを配ってFacebookに投稿して貰うというプロジェクトに従事されました。例えば買い物に使えるというような生活の向上を目指すものとは違い、弱まっていく地域コミュニティをオンラインツールを使って補強しようというプロジェクト。交流の場を用意することで人が集まり、今までにない新しい関係性が生まれて来るのではないか。そんな期待があったそうです。
「プロジェクトを進めていく中で、実際使ってもらうまでには技術的な壁ではないところに、意外と障壁があることに気が付きました。1戸ずつ回って説得しても、本当にそれは今自分たちがやらなければならないことなのかと言われたり。こんなメリットがあるんですよとお伝えしても、それならやってみようという人はごく一部で、実際に使ってもらうにはもっと別の理由が要るんです。集落に行って、お年寄りたちと関わって、これはこうやって使うんですよとか、こんなに便利なんですよという話をする、修士の間はそういうことをやっていました」
修士に行くなら博士にも行きたい、研究者としてやっていきたい。大学院進学の時にそう希望されていた通り博士課程に進み、地域の人たちと関わりながら研究者としての階段を上り始めた衛藤さん。しかしこの頃の衛藤さんは1つの疑問を感じ始めてもいたと言います。
「自分がそこには住んでいないということですね。結構頻繁に行ってはいても住んでいないし、例えば地域活動のような、こういうことを普段やっているということが全く分かっていなかったので、本当にそれでいいのかという気持ちがありました」
そこで衛藤さんは大学のある京都市から車でおよそ2時間半、兵庫県養父(やぶ)市に家を借りて移り住み、自治体からの委嘱を受けて地域住民の課題解決に協力する『地域おこし協力隊』の隊員になりました。普段は養父で活動し、ゼミや打ち合わせがある時には京都に戻る行ったり来たりの生活は、博士課程の間、およそ1年半から2年続きました。
しかし地域おこし協力隊にとって研究は業務外。研究の結果は社会や地域にいずれ還元されると説明しても、簡単には理解が得られませんでした。研究が目的ですと言ってしまうと、本当に地域のためを思ってやっているのか、実験がしたいだけではないのか、どうしてもそう思われてしまいます。これでうまく行く筈だと仮説を立てた新しいチャレンジも、時には失敗することもあります。失敗してもいいと思って始めたことでは当然ながらなく、失敗した理由もきちんと検証してはいたのですが、研究過程でありがちなそんな事情も誰もがすんなり受け容れてくれた訳ではありませんでした。
一方研究発表の場でも「それが研究なの?」「何かの活動でしょう?」と見られてしまいがち。現場での実践と研究を組み合わせてこそできることもあると考えながらそのメリットを伝えきれない……そんなご苦労の日々の中、博士課程を終えて出会ったのが現在の学術研究員のお仕事でした。
京都市と養父市のちょうど真ん中付近に位置する兵庫県篠山市。2016年10月に創設された農村イノベーションラボは、2007年に篠山市と神戸大学が提携した地域連携協定を下敷きとして、篠山市の地域創生戦略の一つの核として、学生など若い人たちの地域に根ざしたビジネスづくり、地域でのチャレンジの支援、そこから新しい農村社会像を描いていくような、価値創造的・実践的な研究に取り組んでいます(神戸大学Rural Innovation Lab、ウェブサイトより)。理論と実践を融合できる願ってもない場所、機会。衛藤さんはこのラボの開設と同時に京都から神戸に研究の拠点を移すことになります。
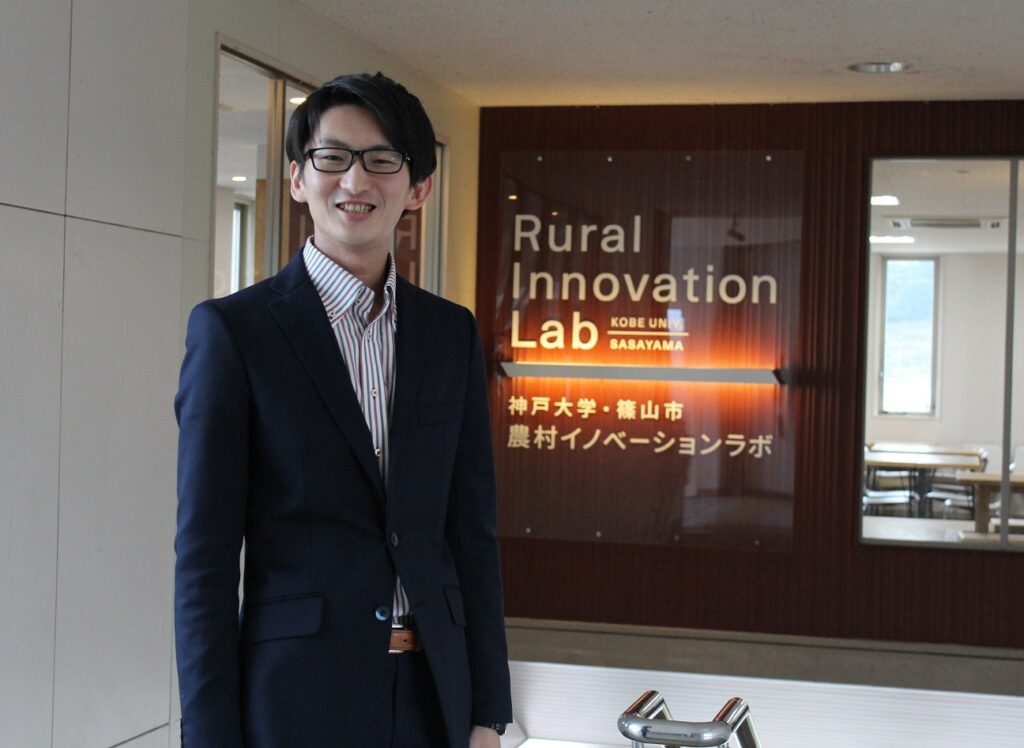
地域の人と関わる『自分』の影響を含めて観察する新しい研究手法
衛藤さんのご専門は農学の中でも農業工学、農業土木と言われる分野。一般には例えば農業の機械化やダムの建設など、工学により近いご研究というイメージがあります。実際にその場所で暮らす人たちと深く関わる研究と言えば人類学や社会学などを想像しますが、農業工学の理論研究の手法としては珍しい、新しいのではないでしょうか?
衛藤さん「アクションリサーチという、大きく言うとそういう領域なのですが、社会学にしても文化人類学にしても、現象を捉えることが基本としてあります。どういう視点から見た時にどうなっているのかを綿密に照らし出す。それがもちろん大切で必要な部分なんですが、僕はそれだけではなく実際に関与するという部分に意義を感じています。多くの場合研究では、自分が与える影響を差し引いて考えるところがあって、中に入って行って一緒に動いたり、自分が影響を与えて変わったことを観察したりすることはあまり行われていません。そうではなくて、ガンガン関わって影響を与えながら、動かしていきながら、動いていくプロセスを客観的に捉えていく。例えば公共政策の中のトランジション研究のような近い研究領域も最近出て来ているのですが、体系化はまだされていなくて、近い関心を持つ人たちがそれぞれの分野の一派として研究している、今はそういう状態です」
既存の研究分野の狭間で――方法論を確立しながら、同時に意義を訴える
新しい手法、新しい分野の開拓について回るのが、研究の意義や意図を伝える難しさ。その困難は研究費の獲得にも影を落とさずにはいられないものでした。
例えば科研費の選考は、専門分野が比較的近い研究者によって審査が行われることになっています(ピア・レビュー)。第1弾の審査では4~6人の審査委員が申請書類を個別に読んで採点を行います。第2弾ではこの採点の結果を元に、十数人~30人程度の審査委員が専門分野ごとに会議を持って、最終的にどの研究に科研費を支給するかを決定しています。これだけ多くの審査員の目に触れるのですから、自分の専門分野とはある程度遠い審査員が入ってくるのは当然ですが、新しかったりオリジナリティが高かったりする分野では近い審査員がほとんどいないという事態も起きてしまうのです。しかも地域の人たちと関わりながらの研究は、進捗のコントロールも難しく、短期間での結果を予測しづらいものでもありました。
衛藤さん「若手研究やスタート支援(研究機関に採用されたばかりの研究者が対象)など、科研費には何度か応募しているのですが難しかったというのがあって、今回採用していただいて素直に嬉しくありがたいです。地域の活動として取り上げていただく機会はある程度ありますが、サイエンス、研究として知っていただける機会は少なく、国際的な発信力も弱いです。国や地域が限定された研究であっても一般化できる部分は国外にも発信できるよう、今回の研究費を使って体制を強化したいと思います」
農村イノベーションラボがテーマとしている農村計画もどちらかと言えば学際的な分野で、農業工学の衛藤さん以外にも農業経済、景観や風景のような造園緑地の分野、空間デザインのような建築学の合計4つの領域から研究者が参加しています。社会への実践、実装が重要だという認識は共通で持っているものの、それぞれの専門分野から持ち込んだ知識や研究手法を繋ぎ合わせた学問であり、体系だった理論はまだあまりありません。強く惹かれる、そして必要性を信じるこの分野に、学問としての理論的な支柱を作り上げるのも衛藤さんの夢のひとつです。
地域への思い、研究への思い。関心を持つ人が繋がれる場所を作りたい。
博士号まで取得しても就職がない、40歳手前まで任期付きのポストでキャリアを繋ぐしかない、いつの日か教授になれても研究以外の業務が多く結局忙殺される――若手研究者を取り巻く環境は、今も決して楽観視できるものではありません。衛藤さんも院生の頃から、苦闘する先輩たちの姿を数多く見てきたと言います。
衛藤さん「そういう視点で考えれば、研究者というキャリアは合理的な選択ではないと思ってしまいますね。よほどやりたい気持ちがなければ、魅力的なキャリアではない。やりたいからやっているんだろうと言われてしまえばその通りではあるのですが、学術としての発展を考えた時にはあまりにひどい状況だとも思います。若手が研究者を目指さなくなって企業や外資に流出してしまい、よほど変人だったり、どうしても研究がしたいという気持ちが強かったりしないと、なかなか選べない選択肢になっているのがもったいないなあと思います。そういうところを解消する仕組みづくりには僕自身関心があって、自分の研究を進めることはもちろん重要ですが、研究の道に進みやすい環境を準備したり整備したり改革したりする活動もやってみたいという思いがあります」
前半の話題に登場した地域おこし協力隊は、もともとは総務省による移住・定住促進のための制度で、そこに住むことを前提とした人たちが最低限の生活費、給与、活動費を支給され、暮らしながら活動する形態を採っています。
「政策としては今、募集人数を拡大しようとしています。制度自体は今までの行政の施策にはなかった画期的な制度だと思っていて、使い方によっては人に投資するという意味と、専門性がない人にもそういう形でチャンスを与えるという意味で二重に面白いと思います。ただ自治体には運営のノウハウがないところも多く、隊員も3年間の任期付きサラリーマンのように考える人が一部で出て来ていて、士気がそれほど高くない、意欲がそれほどない人が混ざってしまう。うまく使えばいい制度なのにもったいないですね」
篠山市では大学と地域が長年連携してきた経験も活かし、地域おこし協力隊の制度を使いながら働ける研究員の制度が今年4月に始まりました。研究自体が協力隊の活動として認められるのが今までとの最大の違い。現在1名の研究者の方が協力隊員として、ご自身の選ばれたテーマで、地域の人たちと関わりながら研究を進められています。

研究の方ももちろんですが、地域での活動も主導する方々にばかり負担がかかるのでは続きません。儲かるという訳でなくても、仕事をしていただいた分は何らかの対価が支払われる形でなければいずれ疲れてしまいます。この先もずっと同じ地域で暮らし続ける方に対して、研究費が足りなくなったので途中ですがやめますというような適当な関わり方もできません。研究者、地域の人たち双方を安心させるこの制度、今後広がって欲しいものです。
「制度は用意できたので、もっと認知されて成果も出るようになればもう少し水平展開できるのではないかと思います。僕たちのような村づくりだけでなく、たとえばパブリックヘルスや地域医療といった領域でも、地域の人たちと関わりながら進める研究に関心を持っている人自体はいるので、そういう方がここを拠点にして研究し、分野の枠を超えて交流できる学際的な場所にここ自体がなっていく、そのための1つのツールとして、今の制度を少し組み替えて使えないかなと思っています」
就職にしても研究費にしても、若手研究者は1度レールから外れてしまうと簡単に元には戻れない不安と困難を抱えています。自分自身も新たな分野を切り拓く若手研究者として歩み続けながら、これから研究を目指す人たちに対してある種の『道』を作りたいという衛藤さん。最後にご自身の夢や、今後の目標を伺いました。
「現場での実践と学問としての理論研究をそれだけで成立させたいですね。研究をしたい気持ちはありますが、どうしてもアカデミアでというつもりはなくて。一番したい研究に適した環境がアカデミアにあればもちろんそこがいい訳ですが、そうでなければ違う道を探るべきだと思っています。今のラボでの活動のようなことを続けながら、それが研究費を生み出して回っていくような仕組みをこの分野で作りたいです。村づくり自体お金にならない、研究もお金にならないのに、お金にならない者同士組み合わせてどうしてお金になるの、無理でしょうと言われていますが何とかしたい。状況としては大変ではありますが、絶望している訳ではなくて、ちょっと希望の線もあるんじゃないかというところを探して行きたいです」
この先に続く人たちへの新しいロールモデルにもなりますね。
「環境としては実際ひどいとは思うんですが、後ろに続く人たちが『研究者ってどうなの? 研究自体は面白いけどどうなの?』と考えた時、意外に何とかなるんじゃないかと思ってもらえるようなキャリアを歩んでいければと思います」
必ずしも大学のポジションに拘らず、地域の方々と関わる中で研究を続ける道を模索する――新たな生き方、新たな研究キャリアの1つの例として、後に続く研究者たちに明るい未来を示したい。衛藤さんの挑戦はまだ始まったばかりです。









